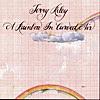MKWAJU/Mkwaju Ensemble【1981】
ジブリではない。
「またジブリか」「もっと芸がないのか」「映写機のおじさんを返せ」「ムカデ人間やれ」など市井からは文句と不平の声が多く上がるが、
マスクがないと生きられないほど汚染された世界を描くこの作品は2020年の締めくくりに最もふさわしいかもしれない。
さて、この映画に限らず、ジブリ映画の丁寧な描写に欠かせないのは久石譲の音楽であろう。
僕は他のアニメ映画とジブリとを隔てているものは彼の音楽と言っていいんじゃないかとも思っている。
指揮からシームレスにピアノ演奏に移るの凄い。
ナウシカを観たことある方なら、この曲を聴いただけで映画のシーンが脳内再生されるはず。
シリアスでありながらも少し愛らしさがある作風が宮崎駿の映像と同質なのだろうね。
この手の音楽に与えた影響は計り知れなく、
こういう幽玄なクラシック的でありつつ、現代的な感性を併せ持った曲はひとまとめにジブリ風と言われるほど。
何せPenguin Cafe Orchestraがジブリ風と呼ばれている文を見たことがある。
逆逆!!順序逆!!!
ただ、これをはじめとしたジブリ関連の仕事であまりにも知られすぎているため、
久石譲というと、ああはいはいジブリの人ね、という感じで捉えられるし、
久石譲は単なる映画音楽家ということで音楽ファンからも一蹴されている感がある。
それは勿体ない!
というわけで今回取り上げるのは久石譲初期に組んでいたバンド、Mkwaju Ensemble!!
例にもれず、久石譲は子供の頃からヴァイオリンを習っていたらしい。
へえ、そうなんだぁとか思っていると先生が鈴木鎮一*1だったらしくビビる。やはり偉人の人生は初手から違う。
結構ヴァイオリンもうまくなったそうなのだが、演奏よりも作曲の方に持ち始め
中学生の頃には既に作曲家を志していたそうだ。早えーー
ただボッチで周りにベースやドラムを弾ける友人がいなかった為バンドができず
結果として現代音楽サイドへと転がっていくことになる。
音大に入った後のある日、友人からあるレコードを貸してもらう。
それがかの有名なテリー・ライリーのA Rainbow in Curved Air。
それまで武満徹やシュトックハウゼンのようないかにもな現代音楽を聴いていた久石氏だったが、このアルバムに衝撃をうけ悩んだ末ミニマル音楽家に転向。
この決定が後々にも大きな影響を及ぼす。
そのミニマルにハマっていたころの久石譲の代表的な作品が今回紹介するMkwaju。
多くの人が「存在は知っているけど実際聴いたことはない」と言う久石譲のミニマムアルバムである。
演奏者名であるMkwaju Ensembleは久石譲が組んでいた打楽器バンド。
メンバーは全員ベルリンフィルの楽団員である上に
このアルバムにはコンピュータプログラミング要員として松武秀樹氏がいる。またお前か。
A面はライヒのように組曲構成になっている。そんな一曲目は表題曲Mkwaju。
いえええい!!ミニマルだあああ!!!!Hoooo!!!
概してミニマルというのはその曲の構成上、機械的になりがちといわれる。
が、このアルバムで久石譲氏が取り上げたのはアフリカのリズム。*2
先の松武氏のプログラムしたドラムに加え人力のドラムもいるらしく
その2つからなるドラム隊が独特のグルーヴ感を出していてかなり人間的である。
この手法は最近だと東京塩麹に受け継がれているのかもしれない。
この「18人の音楽家のための音楽」をアフリカンにしたようなこの組曲は現在では日本でもっとも初期のミニマルミュージックの好例として挙げられ、今でもよく演奏されるそうだ。
ところでさっきからマリンバの残響が歪んでいるが、これはパイプに穴があけられ、そこに紙が貼ってある特殊なマリンバでミトラ・マリンバというらしい。
この前衛的な楽器のおかげで、現代音楽ともポップスともつかない、不思議なこのアルバムの性格がより濃くなっている気がする。
B面はアンビエントな作風へチェンジ。
Mkwaju Ensemble - MKWAJU - Pulse In My Mind (1981)
これの作曲にはなんと乱数表をつかったということ。
ただ、偶然の音楽というよりは構成をしゃんとさせるために使ったらしい。いいね。
東アジアの空気感がほんのりと漂い、やや湿った感じの雰囲気。
まさにジブリ映画で夜や洞窟等のシーンに流れてそうな曲で、なんだか今我々が思う久石譲像に一番近い気がする。
最後にドラムアンサンブルで締めておしまい。
Mkwaju Ensemble – Flash-Back (COCO-7764)
アフリカの民族音楽をミニマルで再解釈したような雰囲気。
確かにClapping Musicってアフリカ音楽っぽいな...と気づかされる。
そもそも、アフリカ音楽に最初に注目して評価を得たのはこのアルバムの前年に出たTalking HeadsのRemain In Lightであろうことを考えると、
このアルバムのコンセプト自体かなり先進的なものだったに違いない。
さてこのアルバムを出した後、久石譲はあることに気づく。
超前衛音楽なのに、それをやっている人たちは前衛的な新しい思考を持っていなかったからなんです。
それで”こういう状況からは、絶対新しいものは生まれない”と思っちゃったんですよ。
それでフッと横を見たら、ロキシー・ミュージックからはブライアン・イーノが出てきて、で、クラフトワークもいてという状況になっていたわけですよ。
彼らはロックをベースにして登りつめてきてミニマル的なことをやってて、僕は現代音楽のほうからきてミニマルをやってたんだけど、両者のやっている内容はそんなに違わなかったんですよ。
それなら飛んじゃったほうがいいやと思って。ポップスというフィールドがすごく新鮮に見えたんですよ。
ポップスの世界に行ったほうが、よりアヴァンギャルドなことができると思ったんです。
そう、クラシックよりポップスの方が前衛ではないかと思い始めたのだ。
その後、JAPANレーベル*3からソロ作品を出したのち、ある映画の劇伴制作にお呼びがかかる。
そう、それこそが風の谷のナウシカである。
それでは最初のYoutubeを見返してみましょう。
よくよく聞くと、字幕くんが解説している通り、確かにミニマムミュージック的な動きをしている曲があったりアンビエントを彷彿とさせる曲があったりする。
ポップスに転向した後も久石譲はミニマム、前衛の精神を忘れていないのだ。
以降、ちょくちょくミニマムのアルバムを作っている。
その名も「ミニマリズム」。
確かにミニマムだが、ポップスで培ったの歌心も忘れていない作品。
こちらも是非。
ちなみに大学時代はクセナキスも好きだったらしい。意外。
(これが久石譲っぽくなるのもミニマルが根底にあるからかもね。)